【男の生き方、人生の楽しみ方】第5回「加藤哲也さん(カーグラフィック代表)」
この連載は2020年9月にスタートしたが、依然としてコロナウイルス感染症は収束しない。「ウィズコロナ」の様相を呈している。
だが、悲観するより、楽観だ。今の環境を嘆いても何も変わらない。どんな場面でも、自分自身の考え方ひとつで人生は変えられる。
今回も、当連載のテーマを体現している人にご登場いただく。天性のポジティブさで、人生の悪路もひるまずにハンドルを握り続けてきたカーグラフィック代表の加藤哲也さんだ。
◇
東京・目黒のカーグラフィック本社。その会議室には2004年のル・マンウイナー、アウディR8のV8レーシングエンジンが鎮座していた。
1960〜70年代生まれのDANTES世代は、70年代半ばから後半にかけて大ブームとなったスーパーカーに熱中した人も多いだろう。男はいくつになっても、クルマや飛行機、電車など、動くものに心躍らされる。筆者も、V8エンジンの咆哮を想像しながら、加藤さんの一言一句に耳を傾けた。
- ■クルマとの出合い
- ■自動車レースと雑誌
- ■演劇青年
- ■テレビの世界へ
- ■カーグラフィック不合格
- ■「しつこい男」
- ■人の記憶に残す
- ■新人の試練
- ■進取の気性
- ■壊しどころと守るところ
- ■信じた道を走る覚悟
- ■「年甲斐もなく」と言われたい
■クルマとの出合い
加藤さんは高度成長期真っ只中の1959(昭和34)年、東京・半蔵門で生まれた。前回の東京五輪の5年前。日本のモータリゼーションに加速度が付いてきた時期である。
「原点は父なんですよ。父は母親(加藤さんの祖母)の大衆食堂の手伝いをしていたのですが、魚河岸などに材料の仕入れに行くのに必要だという口実で日野ルノーを買ってもらったんです。父はそのクルマで僕を横浜ドリームランドや板橋の母方の実家にちょくちょく連れて行ってくれました」
「それと土地柄かな。半蔵門はイギリス大使館に近い。当時は大使館内に子供が自由に入れて、缶蹴りしたりして遊べたんです。そこで自然に輸入車と触れる機会があった。また、わたびき自動車という(大正7年創業の)輸入車の板金塗装の老舗が麹町にあったこともクルマに魅せられたことにつながったと思います」
■自動車レースと雑誌
1966年、7歳だった加藤少年は父親に連れられて富士スピードウェイでインディ500レースを観戦した。これでますますクルマの魅力に取りつかれてしまった加藤少年は4歳年上の従兄らと自動車雑誌の回し読みもしていたという。当時熱中したのはカーグラフィック、オートスポーツ、カーマガジンの3誌だったらしい。
少年の頃からのカーマニア。当然、その後も自動車一筋で人生が進んだのだろうと想像しがちだが、実際の加藤のさんの進路はまったく異なる。なんと、玉川大学の芸術学科に進み、演劇を専攻したのだ。
■演劇青年
「中学生の時、『NOW』という雑誌に書いてあったベルナルド・ベルトルッチ監督の『暗殺の森』(1972年)を観て、完全にやられてしまいました。そして、監督とか演出家になりたいと思ったんです」
加藤さんは自分たちの世代を「背伸び世代」と表現する。「分不相応のモノを求めたい世代」だというのだ。たしかに、ベルトルッチで映画監督を目指そうと思い立つ中学生は今の時代にはいないだろう。
だが、実はもうひとつ大きな背景がある。加藤さんの父親自身が演劇青年で、プロレタリア演劇にハマっており、前田武彦や鈴木清順らと鎌倉アカデミアという演劇の学校に通っていたというのだ。父親は卒業後カメラマンとなり、アメフトの写真などを撮るプロとしても活躍した。さらに、加藤さんの母親も映画好きとあって、加藤さんの演劇専攻はむしろ自然な流れだったのかもしれない。
■テレビの世界へ
映画監督を志して大学に入った加藤さんだが、大学の紹介で働き始めたのはテレビ制作会社。フリーの助監督として仕事を始めた。「当時の映画界はぱっとしなかった」というのがテレビを選んだ理由だ。
だが、当時はお笑いブームの時代。やりたかったドラマの枠はみるみる減っていった。そんな中、新番組開発室に回された加藤さんはアラスカ物語の足跡をたどるドキュメンタリーの制作に携わることになる。3カ月間アラスカに滞在し、オーロラを撮影するためのカメラを光学メーカーと共同開発するなど、様々な体験をした。この時の経験は今も深く心に刻まれているという。
ところが、その後、加藤さんはバラエティー番組班に配属される。
「〇〇の大予言とか、世界の〇〇とかの制作にかかわったんですが、ちっとも面白くない。もうテレビの仕事は続けられない、と思った頃に読んだカーグラフィック誌に求人募集が出ていた。『これだ!』と思い、面接を受けたんですよ」
■カーグラフィック不合格
「でも、落ちたんですよ(笑)。一次が書類選考、二次が一般教養や英文和訳、論文などの試験、そして三次が面接なんですが、三次の面接で落ちたんです。一次、二次で落ちたのなら諦めもつくんですが、面接で落とされたので『なんでだよ!』と思い、当時の小林彰太郎編集長に電話したんです」
その時、加藤さんは25歳。一方、小林彰太郎氏はカーグラフィックを創刊したモータージャーナリストの大御所だ。
臆せず電話した加藤さんもすごいが、小林さんも懐が広い。「じゃあ会おう」と受けてくれたという。そして面談当日、小林さんから、120倍の競争率の中、加藤さんは最後の2人のうちの1人だったということを聞かされる。
「実はカーグラフィックTVをスタートする直前だったんですが、僕はテレビの世界は懲り懲りだったので、『テレビはやりたくない』と言ってしまったんです。それで落とされたらしいことはわかりました」
■「しつこい男」
最初の面会ではそんな話をしただけで別れたというが、その後、カーグラフィックTVの放映を見た加藤さんは思わずズッコケたらしい。
「カーグラフィックギャルみたいのが出てきたり、編集部員が九州の試乗会場から『シュワッ!』とかやらされ、そのまま東京にワープしてるみたいな…。なんだよこれっ!と思い、また小林さんに『なんですか、あれ?』と電話したら、また会ってくれました。でも、その時も話をしただけで採用には至らなかったけれど…」
だが、この「しつこさ」が幸運を呼ぶ。
「さすがに、もう仕事を見つけないとまずいなと思い、タクシードライバーをやるか、マクドナルドでバイトしようかなどと探していた矢先、ちょうど(テレビ制作会社の)送別会の2日前に(カーグラフィックを当時出版していた)二玄社から電話があり、『まだ、来る気ありますか?』と聞かれ、すぐに決めました。編集部員に1人欠員が出たそうです。『しつこい奴がいる』ということで白羽の矢が立ったんでしょう(笑)」
■人の記憶に残す
採用が決まった時のことを思い出しながら、加藤さんは「記憶に残すってことは大事だな」と語ってくれた。
もちろん、きらりと光る何かをもっていなければ、小林さんもあえて二度も加藤さんに会おうとはしなかったはずだ。ただ、筆者自身も感じることだが、魅力的な男たちは皆おしなべてウルトラポジティブ。たとえ壁にぶつかっても、自力で叩き壊していくような、いわゆる「しつこい」タイプが多い。
しかも、その時の加藤さんは、「採用してほしい」という下心ではなく、純粋に子供のころからの愛読誌カーグラフィックのテレビ版に歯がゆさを感じていたのだ。その思いから、小林さんという大御所にも壁を感じることもなく素直にぶつかっていったのだろう。
■新人の試練
晴れてカーグラフィック誌の一員となった加藤さんだが、試練が待っていた。それまで文章など書いたこともなかった加藤さんは、先輩だらけでライバルも多い編集部の中で、自分の陣地をいかに築くかを考えたと言う。
「企画ひとつ通すのも大変でした、あまり大きな企画は出さず、控えめに出して、『よし、やってみろ』となったら間髪を入れずサッと手を挙げるって感じです」
その後、経験を重ねていくと別の壁に突き当たった。
「最初は恐いもの知らずで書いていたものが、2年、3年すると、筆が踊っていない。自分の原稿に納得できなくなる経験もしました。当時の編集長とそりが合わず、仕事を干されたこともあります」
その後、「NAVI」という雑誌を創刊し、編集局長の座に就いた上司が加藤さんを評価してくれて、カーグラフィック誌の副編集長に抜擢してくれた。「そこから、加速してきましたね」。
■進取の気性
前線に戻った加藤さんは、映像の経験も生かしてさらに前に進む。
「例えば、画像を傾けるとか、丸いアウディTTを、柱でも何でもいいから直線を入れて丸さを強調するとか。雑誌の世界ではタブーですが、同じアングルでサイズの緩いのから詰めていく。そんな動画の手法でホンダのS800を撮ったりしましたね」
前例にとらわれず、映像時代に培ったテクニックを雑誌の世界に取り込んでいったのだ。
そんな加藤さんの「座右の銘」を問うと、即答で「僕は暖簾の古い雑誌にいるわけだけど、『壊しどころと守るところのバランスを取ること』かな」と返ってきた。
「カーグラフィックは今年で60周年になります。これまで生き続けてこられたのは、根底にある『進取の気性』が要因だと思うんですよね」
たしかに、確固たるブランドを築きつつ続いている企業は「壊しどころと守るところのバランス」をしっかりと取っている。例えば、羊羹で有名な「とらや」は1501年の創業で500年を超える歴史を持つが、常に「伝統と革新」をポリシーとして事業に取り組んでいるという。永続するブランドのベースに流れる考え方は同じなのだ。
■壊しどころと守るところ
「壊しどころと守るところのバランスをとる」という考え方は個人の生き方にも言える。自分のポリシーを曲げずに貫きながらも、時として過去の自分を否定し、その否定をとおして新しい自分に生まれ変わるチャンスを自ら生み出す。それが、さらなる成長につながるのではないだろうか。
実はカーグラフィック誌も、創刊50周年まであと2年という2010年、「あわや廃刊か」という最大の危機に陥った。リーマン・ショックの影響や出版不況のあおりを受けて、発行元の二玄社が厳しい状態に追い込まれ、会社がインセンティブも退職金もない早期退職者を募ったのだ。
それをきっかけに加藤さんは動いた。二玄社からカーグラフィック誌の商標と事業の譲渡を受けようと決断したのだ。それにより、二玄社には譲渡資金が入るので、退職金が払える。カーグラフィックという加藤さんが幼少時から愛読していた雑誌を存続させることもできる。
■信じた道を走る覚悟
「幸い、僕には古い付き合いの出資者がいてくれた。その人に1年間お願いして出資してもらって譲渡契約がまとまったんです」
とはいえ、サラリーマンだった加藤さんが創刊50年の老舗雑誌を背負っていくことには怖さもあったのではないか。
「そりゃ、覚悟はいりましたが、それ以上に自分だけの問題じゃないわけですよ。二玄社から
スタッフを何人か連れていくつもりでしたから、彼らの生活も掛かっている。プレッシャーよりも、やらなきゃいけないという気持ちが強かったんです」
実は加藤さんは映画監督を目指した頃から基本的には何も変わっていなかった。企画し創り上げることにやりがいを感じる根っからのプロデューサーであり、経営者の才覚がもともとあったようだ。同時に、信じた道を突っ走る、パッションと行動の人なのである。
■「年甲斐もなく」と言われたい
最後にDANTES読者へのメッセージを語ってもらった。
「みんな、いい年をしてるんだから物おじするな、それと出し惜しみするな、かな。インプットも大事だけど、アウトプットも大事だよ。それは仕事もそうだし、遊びもそうですよね」
加藤さんは40歳の時に2輪免許を取得した。「忘れ物を取りにいく」という感覚だったという。その後、マウンテンバイクにも凝り、こだわりのパーツを組み合わせて楽しんでいるそうだ。
やろうと思った時に、年齢は関係ない。「『年甲斐もなく』と言われたいですね」と加藤さんは笑う。
コロナウイルスに恨み言を言っても明るい未来はやってこない。
人生は一度きりだ。諦めたら何も残せない。
今こそDANTES世代は、「年甲斐もなく」と言われるようなチャレンジをしようではないか。
アウトプットしなければ「再始動」などできないのだから…。
この記事のライター
大澤尚宏
リクルートを経て広告プロデューサーとして活動。1995年にバリアフリーライフ情報誌を創刊。2008年にミドル&シニア世代を対象にした「オヤノコトエキスポ」を開催し、2009年に株式会社オヤノコトネット(https://www.oyanokoto.net/)を設立。夕刊フジで毎週木曜日にコラム「人生100年時代 これから、どうする」を連載中。2020年から「日本を元気にする」をテーマに執筆やイベントコーディネート等も始めている。
RECOMMEND
-AD-
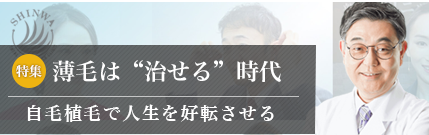
日帰りで薄毛の悩み解消/メスを使わず自然にできる自毛植毛手術 - vol.1
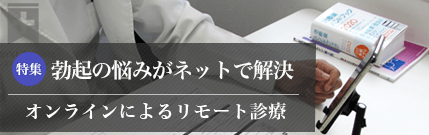
勃起の悩みが自宅で解決/メンズライフクリニックのオンラインによるリモートED診療
薄毛の悩みに新たな選択肢/ヘアタトゥーの実力とは?
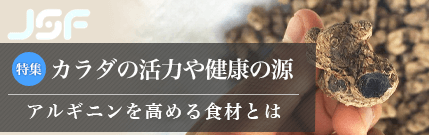
カラダの活力や健康の源/アルギニンを高める食材とは
YouTubeセミナー
-
視聴無料 セミナー

〜アメリカでのテストステロン補充療法〜
詳しくはこちら -

 「男塾」配信セミナー特集
「男塾」配信セミナー特集 -
 【共催】DANTES
【共催】DANTES -
 【後援】日本Men's
【後援】日本Men's
Health医学会 -
 【後援】日本抗加齢
【後援】日本抗加齢
医学会
ダンテス人気記事
2021/01/20
マスターベーションで男性器疾患を発見、実益も兼ねた最新「自慰マシン」
2020/04/01
AV男優になるにはどうすればいいですか【教えて!いろは先生】
2021/09/20
自毛植毛術後の後頭部はどうなる?どれぐらいで生えてくる?
2020/09/17
自毛植毛で後悔! 施術リスク(副作用や後遺症)に潜む悲劇…
2020/04/03
中高年を襲う男性更年期障害チェックリストと高める術
2021/10/09
中高年の性生活の実態調査公表
2020/04/02
ED(勃起不全)は実は大病のサイン、見逃すと怖い事態に
2020/04/02
ED治療薬とは?仕組みから効果まで徹底解説
2020/07/31
ED治療のオンライン診療とは?対応しているクリニック5選
2021/10/16
あなたのLINE、女の子をイラ立たせる「おじさん構文」になっていませんか?
2020/06/12
包茎の種類とそれぞれの手術・治療方法を分かりやすくご紹介
2020/04/03





